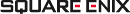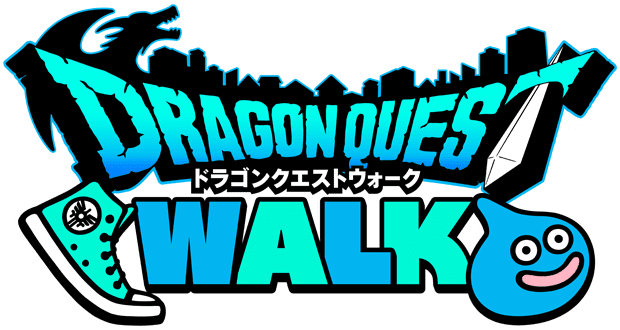スマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」では、ゲーム内の「ランドマーク」と呼ばれる場所に実際に訪れることで特別なクエストを受注することができ、クリアすることで「おみやげ」と呼ばれるゲーム内アイテムを取得することができます。
その「おみやげ」を実際に作って再現していこうというプロジェクトが「リアルおみやげプロジェクト」です。



リアルおみやげプロジェクト第七弾として、株式会社聖護院八ッ橋総本店とコラボレーションした「スライム生八ッ橋(つぶあん入り)」が登場。
にっきと抹茶の生八ッ橋でつぶあんを包んだ定番の「聖(ひじり)」で、ゲーム内のおみやげ「スライムのやつはし」を再現しました。
この機会に是非お召し上がりください。
にっきと抹茶の生八ッ橋でつぶあんを包んだ定番の「聖(ひじり)」で、ゲーム内のおみやげ「スライムのやつはし」を再現しました。
この機会に是非お召し上がりください。

ゲーム内に登場する京都府のおみやげであり、ふるさとスライムでもある「舞妓はんスライム」を、本コラボレーション仕様にアレンジ。
つまみかんざしを八ッ橋にして、櫛は京都の名所を表現しました。パッケージ本体は着物でおでかけする時に使用する和装バッグをイメージして制作しています。
つまみかんざしを八ッ橋にして、櫛は京都の名所を表現しました。パッケージ本体は着物でおでかけする時に使用する和装バッグをイメージして制作しています。


| 商品名: | スライム生八ッ橋(つぶあん入り) |
|---|
| 内容量: | にっき5個、抹茶5個 |
|---|---|
| 売価: | 1,080円(税込) |
| 販売期間: | 2025年5月16日(金)~ 7月15日(火) |
|---|
- 商品が無くなり次第、販売終了となります。
- 販売期間は予告なく変更となる場合があります。
- 将来再販売する可能性があります。
原材料名:
【にっき】砂糖(国内製造)、米粉、小豆、きな粉(大豆を含む)/酵素(大豆由来)、香料
【抹茶】砂糖(国内製造)、米粉、小豆、きな粉(大豆を含む)、抹茶/酵素(大豆由来)、香料
【にっき】砂糖(国内製造)、米粉、小豆、きな粉(大豆を含む)/酵素(大豆由来)、香料
【抹茶】砂糖(国内製造)、米粉、小豆、きな粉(大豆を含む)、抹茶/酵素(大豆由来)、香料
【ご購入いただける店舗一覧】
| 聖護院八ッ橋総本店 熊野店 | 京都府京都市左京区聖護院山王町16
|
|---|---|
| 聖護院八ッ橋総本店 稲荷店 | 京都府京都市伏見区深草稲荷御前町65 |
| 聖護院八ッ橋総本店 岩月堂清水 | 京都府京都市東山区清水2-218 |
| 聖護院八ッ橋総本店 新八店 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町37-17 |
| nikiniki à la gare | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 |
| ジェイアール京都伊勢丹 聖護院八ッ橋総本店売場 | 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 |
| PLUSTA京都幹線中央改札内 | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 2F |
| PLUSTA Bento京都幹線中央改札内 | 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町京都駅 |
| Bellmartアスティ京都 | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 八条口コンコースエスカレーター付近 |
| PLUSTA Giftアスティ京都 | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 新幹線東乗換口 京都駅構内 |
| PLUSTA Gift京都幹線中央改札内 | 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町京都駅 |
- こちらの商品の販売は終了いたしました
販売日:2025年6月1日(日)~ 6月30日(月)
- 1日50個販売
八ッ橋の新しいお召し上がり方を提案するブランドとして誕生した聖護院八ッ橋総本店のセカンドブランド「nikiniki」では、生八ッ橋でスライムを再現した「nikinikiスライム」を1日50個販売いたします。
事前にnikinikiオンラインショップにて抽選販売を実施いたします。応募に関する詳細は「nikinikiオンラインショップ」をご確認ください。
事前にnikinikiオンラインショップにて抽選販売を実施いたします。応募に関する詳細は「nikinikiオンラインショップ」をご確認ください。


【nikinikiスライム 抽選販売実施期間】
| 6月1日~7日販売分 | 受付期間:2025年5月19日~5月25日 |
|---|---|
| 6月8日~14日販売分 | 受付期間:2025年5月26日~6月1日 |
| 6月15日~21日販売分 | 受付期間:2025年6月2日~6月8日 |
| 6月22日~28日販売分 | 受付期間:2025年6月9日~6月15日 |
| 6月29日~30日販売分 | 受付期間:2025年6月16日~6月22日 |
【お受け取り店舗】
| nikiniki à la gare(ニキニキ ア・ラ・ギャール) | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 アスティ京都 京都駅八条口1F 京都おもてなし小路内 |
|---|

- お申し込み受付は終了しました
- おひとり様1個までご購入いただけます。
- 受付期間終了後3日以内に当選された方のみ、メールにてご連絡をいたします。
- 当選確定後のキャンセル・受け取り日の変更は出来かねます。
- 料金は前払いとなります。
【店頭販売に関して】
店頭でのご購入に関するご要望を受けまして、6月9日(月)より平日に限り【 1日10個 】店頭にて販売いたします。
数に限りがございますので、売り切れの場合はご容赦ください。
店頭でのご購入に関するご要望を受けまして、6月9日(月)より平日に限り【 1日10個 】店頭にて販売いたします。
数に限りがございますので、売り切れの場合はご容赦ください。
店頭での販売期間:2025年6月9日(月) ~ 6月30日(月)
- 平日のみ販売

本社:〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町6
電話:075-761-5151
創立:元禄二年(1689年)
電話:075-761-5151
創立:元禄二年(1689年)
八ッ橋が誕生したのは、元禄二年(1689年)です。
江戸時代前期、箏の名手であり作曲家でもあった八橋検校は、「六段の調べ」など数々の名作を生み出し、近世筝曲の開祖と称えられています。
歿後、黒谷の金戒光明寺にある常光院(八はしでら)に葬られましたが、墓参に訪れる人は絶えることがありませんでした。 そのため検校没後四年後の元禄二年、琴に似せた干菓子を「八ッ橋」と名付け、黒谷参道にあたる聖護院の森の茶店にて、販売し始めました。 現在の当社本店の場所にあたります。
以来、355年余りに渡り、当社は八ッ橋を製造し続けています。
続いていくということ。
続いてきたということ。
継続ということの本当の意味を常に忘れることなく、私たちはこれからも京都で八ッ橋を作り続けていきます。
江戸時代前期、箏の名手であり作曲家でもあった八橋検校は、「六段の調べ」など数々の名作を生み出し、近世筝曲の開祖と称えられています。
歿後、黒谷の金戒光明寺にある常光院(八はしでら)に葬られましたが、墓参に訪れる人は絶えることがありませんでした。 そのため検校没後四年後の元禄二年、琴に似せた干菓子を「八ッ橋」と名付け、黒谷参道にあたる聖護院の森の茶店にて、販売し始めました。 現在の当社本店の場所にあたります。
以来、355年余りに渡り、当社は八ッ橋を製造し続けています。
続いていくということ。
続いてきたということ。
継続ということの本当の意味を常に忘れることなく、私たちはこれからも京都で八ッ橋を作り続けていきます。
© SHOGOIN YATSUHASHI CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED.